
私の接骨院の開業医時代
ピーク時には
朝5時から医院に患者が並び、
8時には窓口を開けて受付開始
スタートから番号札を配布して
午前と午後の部で50ずつ
つまりは100人分を
一気に受け付け。
飛び込みで外来も来れば
毎日が戦場となるわけで、
これだけ臨床が多い生活を
12年も続けたら
患者さんに「ある種の傾向」が
見えてきて、
それをタイプ別に
分類できるようになったとしても
生産性を重視しようとする行動においては
全く不思議なことではありません。

外胚葉型は
痩せ型でストレス多め
マニュピレーションは
比較的強めでも全然OK
内胚葉型の人は太めで
体格の割に刺激には弱く
筋力テストはスケール3以下
そして、中胚葉型は
筋肉質だが内臓弱め
血圧が高くて
電気刺激にはめっぽう強い
他にも、タイプ別にSやPなど
挙げたらキリがないのですが、
当時の知る限りでの
「傾向と対策」は
都合の良いカテゴリーに分類して
仕事をしていました。
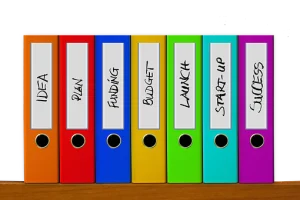
で、ついには
タイプ別治療法という
院内マニュアルが完成。
しかし不思議なことに、
当時はこれでほとんどの症状が
改善されたのです。
(なぜ効果があったのかは物理的に証明できます)

しかしながら
コンスタントに
来院数が100を超えたあたりから、
自分の分類には当て嵌まらない
セオリー外の混合タイプが
続々と来るようになり、
一度1つの歯車が狂い出してから
どっぷりと深みにハマります。
今度は全く治せなくなるのです。

まるで
チェスを覚えた少年が
無邪気にプレイした頃には
勝てていても、
徐々にその駒の特性や戦略を
知っていくほどに
考えすぎて勝てなくなる
という事例にもよく似ています。

同じような経験で、
私が高校の授業の中で
覚えた剣道も、
「六三四の剣」を読んでいた
という理由だけで
周りと比べても
どんどんと強くなっていき、
授業中の稽古では
向かう所敵なし。
一介のバスケ部員が
剣道部に勝ってしまって、
顧問からスカウトされた
ことすらあります。

その後、基礎の大切さを知り
技の正確性を求めるようになってからは
なぜか
負けが続くようになり、
その奥深さを知って
剣道は辞めてしまいました。
(易経でいう乾為天ですね)

話を戻しますが、
つまり、どんなに素晴らしい発見があり
マニュアルが出来上がったとしても、
日々研究しなければ
間違いに気づくことさえ出来ずに
成長しないのです。

タイプ別に患者さんを分ける行為は
非常に偏った考え方であり、
例えば、
カイロプラクティックでいうところの
トムソン・ディアフィールド分析の
頚椎症候、マイナス骨盤、プラスDなど
型に嵌まったやり方だけでは
患者さんを不幸へと導くだけでなく、
結果的に構造を
メチャクチャにしてしまうことだって
考えられるということです。
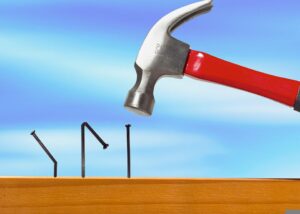
もし、ディアフィールドで
マイナスの兆候が見られていても、
たとえ目安となる圧痛ポイントが
全て揃っていたとしても、
疑うことを忘れずに。
トムソン・ディアフィールド分析が
発展もせずに
そこで歴史が止まっているのが
何よりの証拠です。

そして、1つとして
同じ症例はないと思って
患者さんに触れることを
意識することが大切です。
目に見えていることが
全て真実とは限りません。

とはいえ、
現代人には唯一と言っていい
共通の悩みが
傾向として存在していますが
みなさんはお気づきですか?
それは「食いしばり」です。
次回はそちらにフォーカスして
講じたいと思います。
