この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

(再生ボタン▷を押すと音声が流れます)
ここでは「概念の共有」から
始めていきましょう。
まずはこれだけ
知っていただけたら、
共通言語で
話がしやすいという
4つの概念をご紹介します。
1.「定量的PDCAサイクル」
2.「弁証法」
3.「アドラー心理学」
4.「TOC(制約理論)」
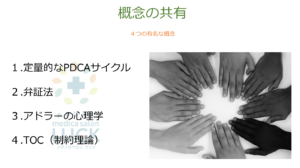
これらは全て
有名なものばかりです。
ちなみに
4つ全てを知っている方は
どれくらい
いらっしゃいますか?
または
逆に1つも知らないという方は
いらっしゃいませんか?

人に対して説明もできるほど詳しい
という方がいれば、
コンテンツにおける私の役割はないので
その方にバトンを渡しますが、
私なりに、知らない方にも
分かりやすく説明したいと思っていますので、
もし、知ってるという方は
読み飛ばしていただいても構いません。

ですが、
どれか1つを知るだけでも
大きく人生が変わるような
どれもが壮大な概念なので、
もし知っていたとしても
学びを深めるという意味で、
どうかお付き合いいただけたら
と思います。

これらは一つ一つのテーマだけで
書籍が何冊も出版されていたり、
大学の論文が
何本も書かれているような、
ものすごい
重厚な内容なのですが、
ここでは分かりやすく
凝縮して説明しますので、
もし、4つの概念のどれかに
興味が湧いた場合には
それぞれ参考書などを
独自に勉強していただき、
肉付けをしていってください。
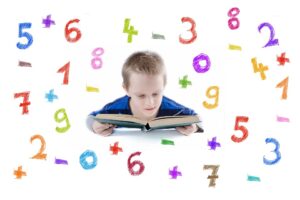
では、まずは
これら4つを理解する前に、
人間の認知システムについても
簡単に共有しておきます。
先にもお伝えした通り
私たちは、
ものを見たときに
目で捉えたときに
それをそのまま脳で解釈することは
出来ない仕組みになっています。

解釈する前には必ず
「フィルター」というものを
通しているからです。
人は「概念」を使って
世界を切り取っている
と、認知言語学の世界では
言われていますので
画像の写真のように
テーブルの上には
MacBookがあって
手帳があって
コーヒーがあって
スマホがあって
というふうに、
私たちは概念を
「覚える」ことで
モノとモノとの境界を
区切って判断している
ということになります。

ヒトはこれを
「言語」を使って行なっている
と言われています。
なので、
「失語症」といわれる疾患
いわゆる言語を司る脳の部分が
損傷してしまった患者では、
視界は働いていても
視覚でそれを捉えていたとしても
モノとモノとの区別が見分けられずに
身動きが取れなくなる
という事象が
確認されています。

概念のフィルター
というのは、
後天的に
生まれてから
様々な経験をしていく中で
身についていきます。
なので、
私たちが育った環境とか
受けてきた教育とかによって
特定の何かに緻密になったり
特定の何かに雑多になったり
しているのは、そのためなのです。
次のお話は、Day.12「文化の違い」です。
