この記事を読むのに必要な時間は約5分です。

脳への連続的な刺激によって、
シナプスは固定され、記憶に残りやすくなる
という特徴の他に、もう一つ
重要なことがあります。

それは、一部の刺激で
どこか1つだけが発火したとしても
回路にはならない
ということです。
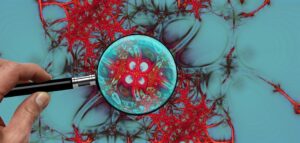
別の部位と別の部位が
発火することで、
そこに電気が通る
というイメージ。
その辺の理解を深めて、
連続して
発火させるためには
脳に刺激として
認知させなければいけないので、
受け身の学習では
なかなか発火しないのです。
なので、
「主体的」に行うということが
かなり重要になってきます。
自分で自主的にやることで
脳の発火は
断然起こりやすくなります。

これらの
脳の特徴がわかると、
私たちが「理解」したり
「記憶」に残したりするそのメカニズムに
ある仮説が立てられます。
要は「回路にしているかどうか」です。
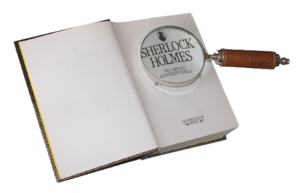
一時的な通電だと
「回路にならない」
なので、必ず
連続して発火させることが重要
ということは、一夜漬けが
一時的な記憶にしかならない
という特徴も
理解できてきますよね。

私たちの頭の中には
記憶というものを
長時間保存しておける場所はなく
それを、回路にしないと
記憶には残りません。
一部分の発火では
回路にならないので、
別の部位と発火させることが
重要だということです。
なので、
仮に一夜漬けだとしても
もし別の概念の何かと繋がれば、
記憶には残りますよね。

私たちが
「記憶する」とか
「理解する」という本質は、
「2つ以上の概念の中に
関係性を見つけること」
ということで
定義づけができます。
繋がりの中でしか
理解はできないし、
繋がりの中でしか
記憶にも残らない
ということです。
これこそが
認知言語学が明らかにした
「人間は差分にしか反応できない」
という分節化の部分に
対応してきます。

こんな話をすると
決まって必ず
「具体的にどうやったらいいのか
難しくてよくわからない」
という声が
多く寄せられますので、
私が具体的な何かを学ぶ時に、
どんなことを意識してやっているのか
を、皆様に共有いたします。

それは
「2つの概念の対比」です。
何かを学んだ時や
何かを体験した時には
自分の中に既にある
別の部位との関係性
を見つけようとします。
つまり、
共通点とか
相違点というものを
なるべく見つけるところから
入ります。
「以前習ったアレと同じかなぁ」
とか
「前に受けたコレとは違うな」
とか
必ず比較をしています。
なので、
今まで勉強してきた知識や
様々受けてきた整体や
カイロプラクティックの経験が
もう既に私の中では
概念として持っているので、
次々と新たな医説が
出てきたとしても
その見え方は
他の方々とはまるで違うわけです。

バイタルリアクトセラピー を
創始者の山﨑先生から習った時も
多分、他の受講生や
既存の弟子の先生方とは
全く違った観点でとらえていて
全く違う見え方だったと思います。
そのため、協会員の中でも
私は異端児扱いでしたが、
それまで私がダウンロードしてきた
様々なフィルターや概念が
バイタルリアクトセラピーを学んで
点と点とで繋がっていったので、
その成果を
次々と学会内で発表し、
山﨑先生から直接認められた
アドバンス(上級)の称号を
得ることが出来ました。
次のお話は、Day.32「概念の対比」です。
