この記事を読むのに必要な時間は約5分です。

(再生ボタン▷を押すと音声が流れます)
概念のフィルターの増やし方を
十分学んだ上で、
「これは知っておくべき」と
私が思っているものを
先のタイトルで
4つほど挙げましたが、
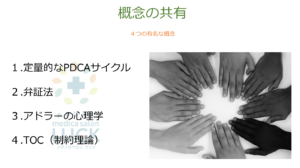
そのうちの一つが
「定量的PDCAサイクル」です。
PDCAサイクルというのは、
理系の研究者たちが
よく使っている概念なのですが
近年では、
経営改善を目的とした
経営コンサルたちが多使用しています。

Plan
Do
Check
Action
その頭文字をとって
PDCAと呼ばれていますが、
「Plan」というのは
計画を立てる
「Do」は
実行を意味し
「Check」は
検証をして
「Act」で
改善をすること

つまり、この Plan→Do→Check→Act の
サイクルを何回まわすかで
「結果」というものが
どんどん洗練されていきます。

これは多分、
日常の中の様々な場面で
皆さん遭遇しているはずです。
「明日はもっと改善しよう」と
思った経験が誰しもあるはずですが、
この「改善」をするときに
大切な約束事があるということを
皆さんはご存知だったでしょうか?
それは
必ず「定量的」に
やらなければならないということ。

定量的というのは
「量で計る」という意味です。
それを数字にしているかどうか
という、本当に大事な部分です。
この反対の概念というのが
「定性的」となります。
定性的というのは
対象の変化に着目すること
なので、数字には出ません。
いわゆる「感覚」として
物事をとらえているわけです。
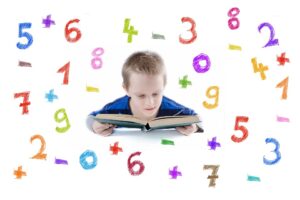
「昨日飲み過ぎちゃった」
「先月は出費が多かったわ」とか
「その前日に比べたら
たくさん飲んだ気がする」とか
「前月と比較したら
だいぶ余計なお金を使ったかな」とか
これは数字ではなく
感覚で物事を捉えた一例です。

定性的に改善してしまうと
必ず曖昧さが残ります。
実際に「昨日よりも頑張ったな」
と思っていても、
数字にしてみるとそうじゃなかった
というのは、よくありますよね。

なので、
改善をするのであれば
「必ず数字にする」
というのが鉄則になります。

もし、タバコが
やめられないのであれば
今まで
1日何本吸っていたのか
先月よりも何%
タバコを控えることが出来たのか
ちゃんと紙に書いて残してください。

あるラーメン店では
「今月はめちゃくちゃ混んだな」と
1ヶ月を振り返り、
来客数を集計してみたところ
なんと、ヒマだった前月の方が
実際の売上数字が良かった事に
気がつきました。
これでは来月さらに混み合って
忙しくなったとしても、
売上自体は良くならない
かもしれませんよね。
原因を早く見つけて
改善しなければ、
非常に効率の悪い経営と
なってしまいます。

こんなふうに
ちゃんと数字にするという部分が
とても大切なのです。
改善のプロセスには
必ず「定量的」というものが
セットになっている
ということを
しっかりと覚えておいてください。

そのために
当院では必ず、患者さんの
初診時の検査データを数値化して
記録紙に残しています。
その数値が変化していくのを
目で見てわかるように
毎回の検査データを比較した上で
定量的PDCAの「改善」をしていきます。

よくある接骨院でのやりとりで
「今日の調子はいかがですか?」
「まあまあです」
とか
「はい、今日はこれでOKですよ!」
「おかげさまです」
とか、
その時の感覚的な変化だけを
追いかけてしまっていて
結果は非常に曖昧となります。
広義の意味では
PDCAなのかもしれませんが
それでは単に同じところを
繰り返して回っているだけの
ゴールの見えないサイクルとなり、
そんな方法では
私が考えている「改善」には
到底至りません。
なので、当院では
定量的な検査を取り入れているのです。
次のお話は、Day.16「第二領域思考」です。
